AIエージェントを用いた業務自動化の価値を「正しく」伝えたい業務変革に与えるインパクトと導入における現実解──UiPath セントラル・チーム リーダー 市川義規に聞く
Share at:
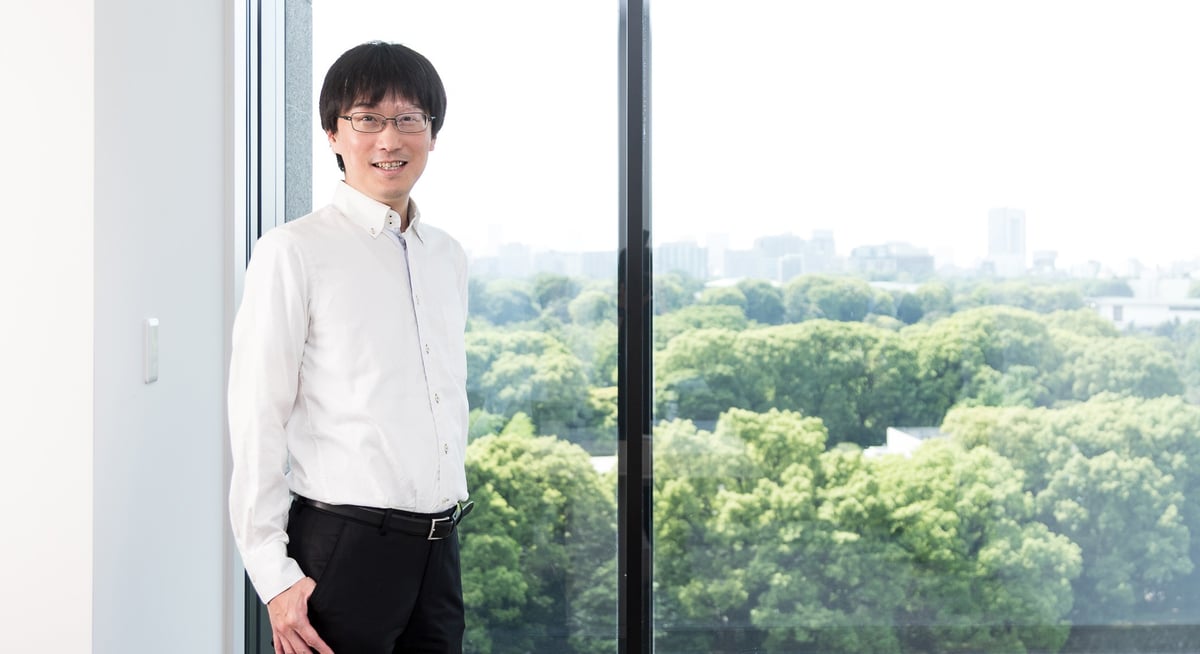
UiPath Japanでは年に一度、社員および幹部推薦により「当社を代表する社員はこの人!」というメンバーを、「Best UiPather」として表彰しています。2024年度、このアワードを受賞したのは、セントラル・チーム リーダーを務める市川義規でした。市川は現在、AIエージェントを用いた業務自動化ソリューションである「エージェンティックオートメーション」のエキスパートとして、その価値をお客さまに提供しており、その功績によりエージェンティックオートメーションの導入支援を加速するため新設されたAgentic Virtual Teamのリーダーに就任しました。今回は市川に、AIエージェントが今後どのような発展を遂げていくかについて、具体的なユースケースを交えて見解を語ってもらいました。
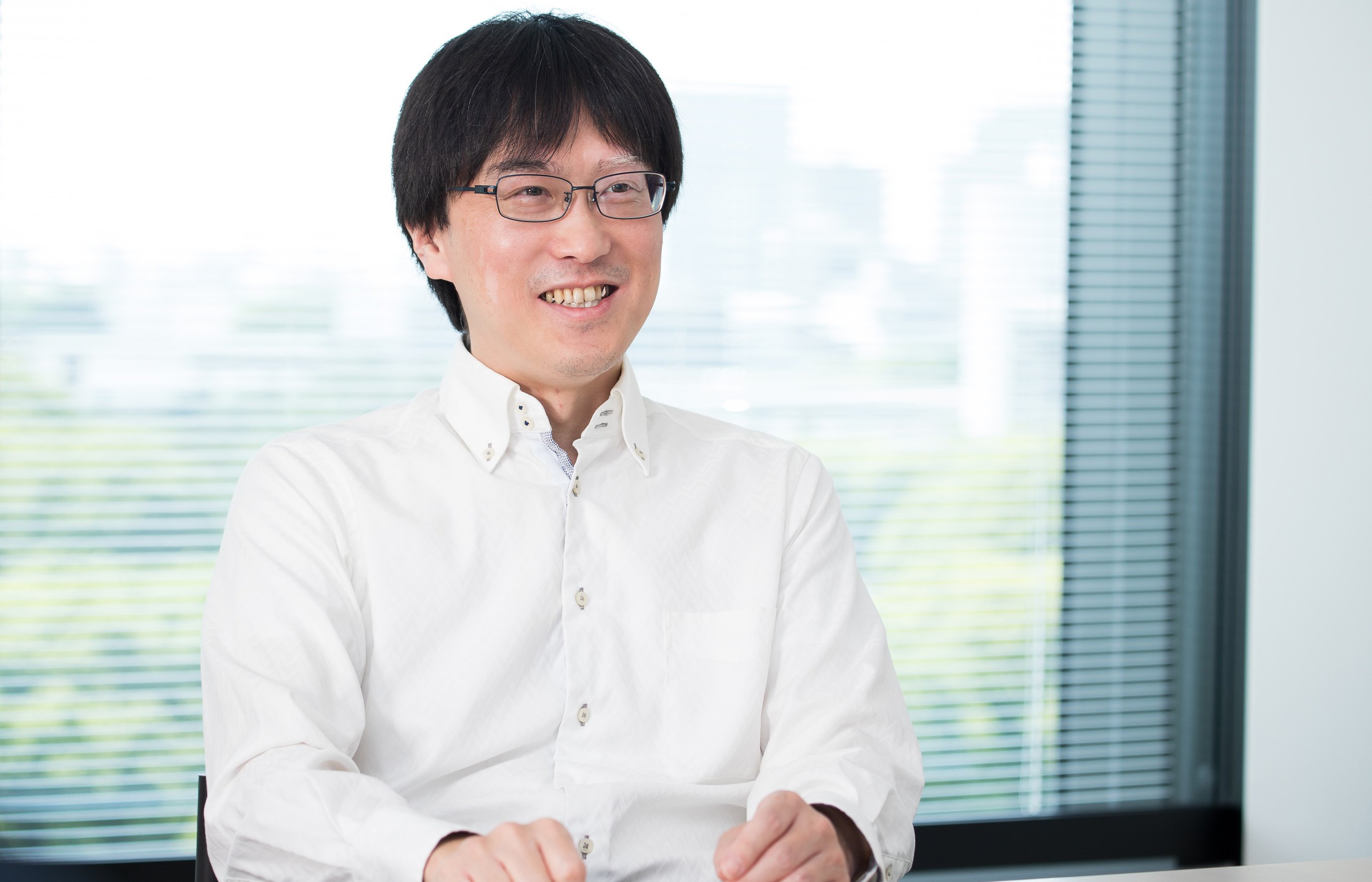
UiPathソリューション本部Agentic Virtual Team セントラル・チーム リーダー 市川 義規
BPMとRPAでは解決できなかった課題生成AI×AIエージェントなら突破できる
前職では複数の外資系ベンダーで、業務プロセスのモデリングや実行、監視システムであるBPM(Business Process Management)やロボットのように人の操作を模倣して業務を代行するRPA(Robotic Process Automation)に関するソリューションを手掛けてきた市川。しかし、当時は技術面の制約に阻まれて、望んだ効果をなかなか発揮できないことに歯がゆい思いをしていたといいます。市川は、今回のお題である「エージェンティックオートメーション」の価値を説明するために、少々前の出来事から語り始めます。
「2000年代後半ごろ、『業務フローを描けば、それがそのままシステムとして動作する』とうたってBPMが流行しました。ところが、人が読んで理解できる業務フローと、システムで実行できる厳密な業務プロセスの間の乖離(かいり)は大きく、うたい文句通りには実現できませんでした。その後、2010年代に欧州から米国に向かってRPAが登場し、その導入までの迅速性とコストの低さから、システム開発やアウトソーシングに続く“第三の労働力”として大きな期待を集めました。その期待値は、かつてBPMが集めていたものと重複するところがあったように思います。一方で、RPAは開発が容易であるがゆえに、深く考慮・設計せずとも実装できてしまいます。そのため動作の安定性や効率性に課題を抱え、運用に負荷がかかるケースがありました。加えて『人の操作を模倣する』と言っても、あくまでルールベース・決定論的な仕組みなので、人が細かく定義した通りに振る舞うだけで、例外的なデータ・操作には極めて弱い仕組みでした。このような特徴から、基幹系システムに見られる堅牢な仕組みを期待するユーザー・技術者からは失望の声もあり、“技術的負債”とみなすような厳しい意見もありました」。
市川はこうした課題を解決できる技術として注目を集めているものこそ「生成AI(人工知能)」であり、生成AIにさまざまな機能・データを「アドオン」して自律的に業務を実行する「AIエージェント」なのだと言います。BPMの時代には「人の考える業務手順」と「システムとして実装する厳密なコード」の間にギャップがありましたが、AIエージェントの自律性がこのギャップを埋めることができます。すなわち、人が用意した業務手順に沿ってある程度の行間はAIエージェントが気を利かせて埋めてくれるわけです。RPAの時代には厳密に人が定義した内容から少しでも逸脱してしまうと、ロボットは実行不能に陥りましたが、AIエージェントならそれも救うことができます。つまり、ファイルの形式やデータの「揺らぎ」、画面の表示内容に変更があったとしても、AIエージェントが臨機応変に例外をさばいてくれるのです。
UiPathでは、従来のBPMやRPAといった製品群にAIエージェントを組み込んで業務を自動化するソリューションを「エージェンティックオートメーション」として提供しています。これにより、BPMやRPAが抱えていた制約を克服しつつあるのです。
「エージェンティックオートメーションに含まれる『Agent Builder』というツールを使えば、自然言語を用いてAIエージェントを容易につくることができます。『Healing Agent』というツールを用いると、ロボットの実行エラーをAIが自動的に解決できるようになります。弊社が提供する先駆的なエージェンティックオートメーションを通じて、日本企業のさらなる業務効率化・自動化を支援したいと考えています」。
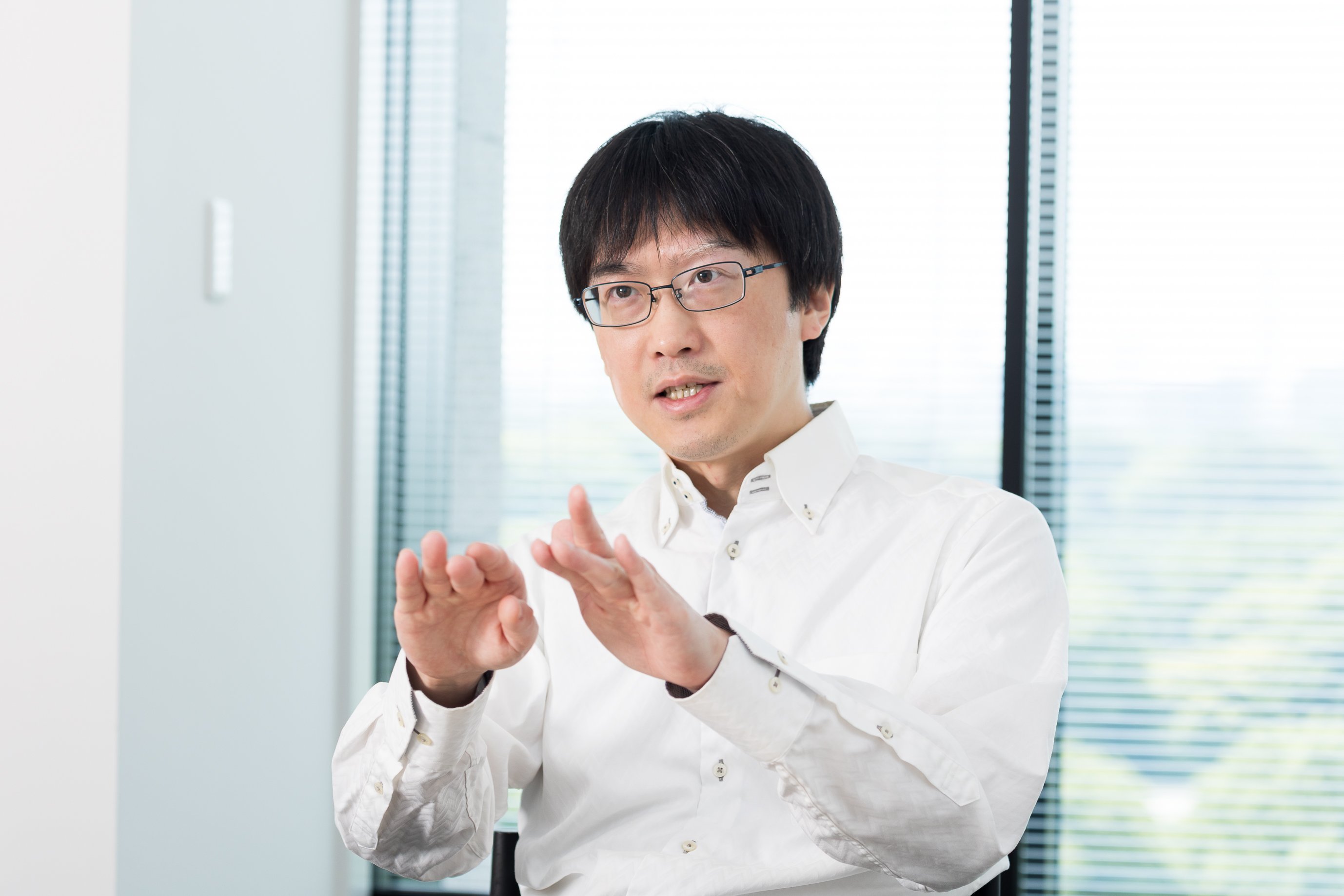
エージェンティックオートメーションの可能性を求めて2200のAIエージェントを分析・評価
ただ、現時点のAIエージェントは概念や機能に関する情報が盛んに発信されている一方で、事例やユースケースといった情報が乏しく(情報の非対称性)、「このままでは一時の流行に終始し、幻滅されてしまうのではないか」という危機感も抱いていると、市川は明かします。
「生成AIは衝撃をもって世間に迎えられたものの、日本企業の業務現場ではまだ浸透が進んでいません。生成AIの登場からほどなくして、LLM(Large Language Models:大規模言語モデル)の回答精度を向上する『RAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)』といういわば“第二世代”の生成AIが出てきましたが、やはり当初期待されていたほどには活用されていません。そこで今、新たに注目されているのが、AIエージェントが自律的に状況を判断してタスクをこなす“第三世代”の生成AIです。現在、業務に役立つユースケースの確立が急ピッチで進められています」。
UiPathでは、この第三世代の生成AIとしてエージェンティックオートメーションのユースケースの確立に世界規模で取り組んでいます。AIエージェントを実装するための製品・Agent Builderを2024年12月から2025年3月までプレビュー公開し、4000名以上のユーザーと、150社以上のお客さまに体験いただきました。この結果として、2200のAIエージェントが実装されました。併せて、UiPath社内では米国・欧州・アジア・日本の各拠点でユースケースを発掘する「Agentic Hackathon」を開催。これらの活動で発見されたエージェンティックオートメーションのユースケースは業種・業界別に分類され、日本のお客さまが参考にし、導入できるように汎用化・展開が進んでいます。
発掘されたユースケースを適用できる業務は多岐にわたります。中でも調達や購買、請求書処理などの業務において多数のユースケースを見いだすことができました。
例えば請求書の内容を照合する業務の場合です。まず、AI-OCRを用いて請求書を自動的に読み取り、内容が正しいかどうかをルールベースのロボットで確認します。次にロボットが「不整合」と判断したものをAIエージェントによって再度調査・分析・解決し正否を判断させ、担当者に結果を通知します。こうした仕組みを開発・評価したところ、かなり高度な自動化を実現できることが分かりました。
見いだされたユースケースに共通の特性があるとすれば、①文書の読取り後の処理②分類やコードの割り当て③調査・解決・報告――であろうと市川は話します。ただし、現時点では業務のすべてを生成AIやAIエージェントで自動化することを考える段階にはない、と市川は指摘します。
「AIエージェントにさまざまなタスクを自律的に処理させることで、これまでにないほど広範な自動化が実現します。しかし、それでも人間によるチェックが必要な部分はどうしても残ります。また生成AIではなく、ルールベースのロボットやBPMといった従来の技術の方が適したタスクもあります。そのため少なくとも現時点では、これらの既存のテクノロジーや人手をAIエージェントと組み合わせた使い方が現実的だと考えています」。
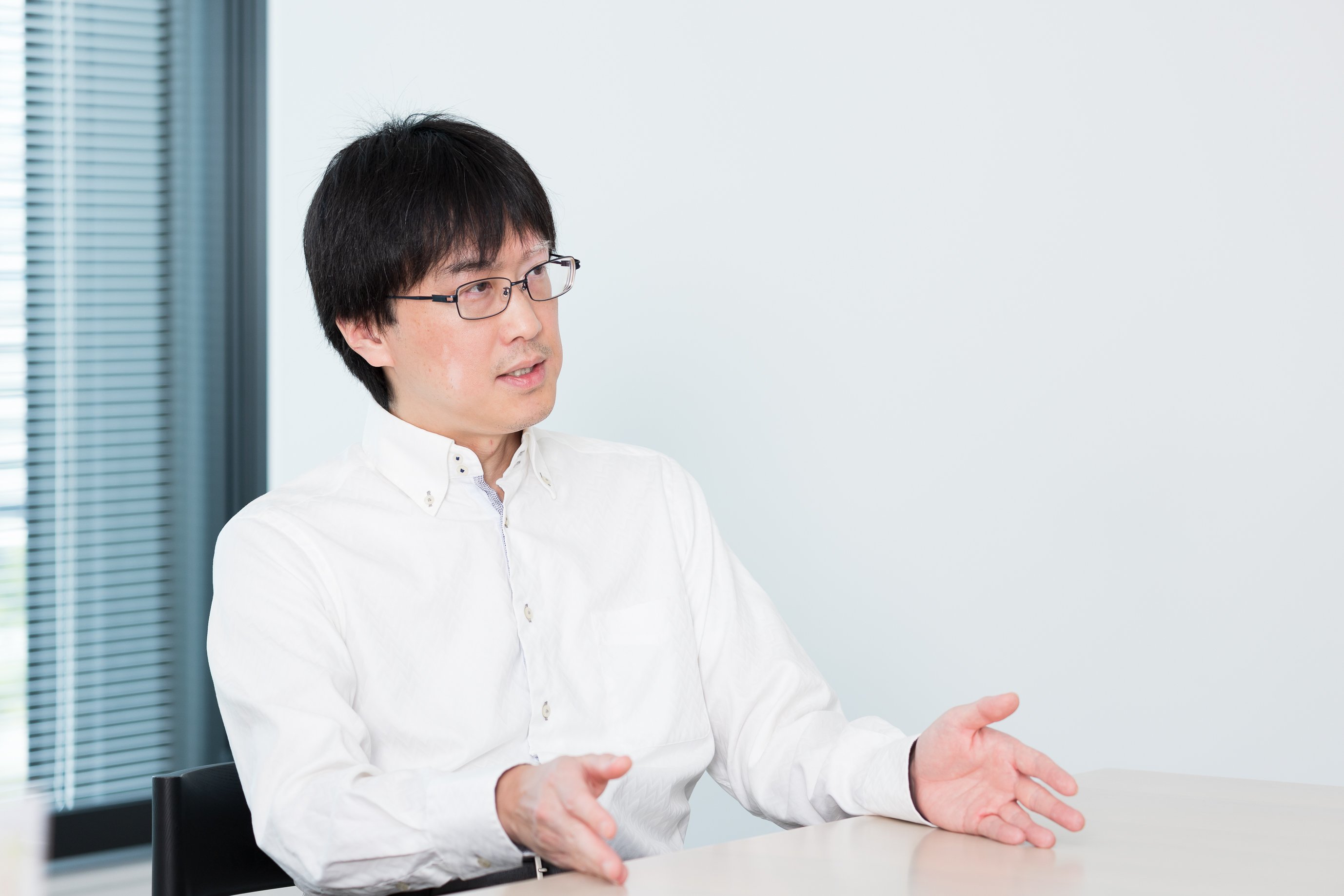
「Best UiPather」受賞者として目指すもの汎用の先進技術よりも企業の業務変革を志向
生成AIの技術は日進月歩で進化を遂げており、各ベンダーが互いにLLMの性能向上やAIエージェントの開発プラットフォームの整備にしのぎを削っています。将来的には生成AIの飛躍的な性能向上に伴い、AIエージェントがより広範な業務を、ひいては業務の全体を自動化できるようになる可能性も十分にあります。ただ、市川は「個人的な見解としてはLLMの性能向上やAIエージェントの開発プラットフォームに過度な期待をもっていない」と語ります。
「あくまで私見ですが、生成AIの進化はLLMに『アドオン』を追加することによるもので、LLMそのものが爆発的に賢くなっている印象はありません。何か非連続的なイノベーションがない限り、人間と同等の学習能力や意思決定力を持ついわゆる『AGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)』の普及までには、やはりまだまだ時間がかかるのではないかと思います」。
UiPathが提唱するエージェンティックオートメーションは、こうしたAIの進化シナリオからは少し距離を置いていると市川は続けます。UiPathがエージェンティックオートメーションによって目指すものは、技術そのものよりも技術を用いていかに業務を変革できるか、ということ。これは市川の信念とこれまでの活動につながる考え方でもあります。
「AGIの普及を目指して長期的なロードマップを描くアイデアは非常に重要で、素晴らしい取り組みですが、UiPathは創業当初から定型業務と言われる企業の事務仕事やオペレーションを自動化し、“目の前の”業務課題を解決するための技術を追求し続けています。エージェンティックオートメーションも例外ではありません。万能なAGIを目指すよりも、すぐにでも業務オペレーションの効率化・自動化に寄与できるテクノロジーを志向し、既存技術や人による作業と組み合わせることで高度な自動化を目指しています」。
「同時にひとつ言えるのは、生成AIやAIエージェントの技術が標準化されてきていることです。製品ベンダーを横断した技術の標準化としてA2A(Agent2Agent)やMCP(Model Context Protocol)が提案されており、UiPathもこれらの標準技術に準拠していきます。仮にUiPathよりも飛躍的に優れたAIエージェントが登場したとしても、標準プロトコルで連携していけば、お客さまにとっては有用なエージェンティックオートメーションになるでしょう」。
市川は今後、エージェンティックオートメーションが持つ価値を「できるだけ多くの日本企業に届けていきたい」と意気込むとともに、そのためには「正直できちんとしたビジネスを手掛けたい」と語ります。
「日本のIT業界では得てしてベンダーが夢物語を語りがちで、ユーザー側もその実現は難しいと薄々感じながらもどこかで期待し、安易に製品やツールを導入してしまうことが実はあるのではないでしょうか。そうではなく、AIの真の価値をお客さまにきちんと説明し、それをしっかり理解していただいた上で正しく使ってもらうことが大事だと思うのです」。
BPMやRPAだけでは、自身が目指したお客さまの業務変革を達成しきれなかった過去があるからこそ、市川はそれらを組み合わせて速効性のある業務効率化・自動化を実現しようとしています。最後は力強く、こう語ってくれました。
「UiPathのエージェンティックオートメーションで、これまで自動化が難しかった領域も自動化し、ひいては生産年齢人口の減少と人手不足に直面する日本社会の持続可能性や経済発展に貢献していきたい。自身のこれまでのキャリアの集大成として、エージェンティックオートメーションに向き合っていく思いです」。
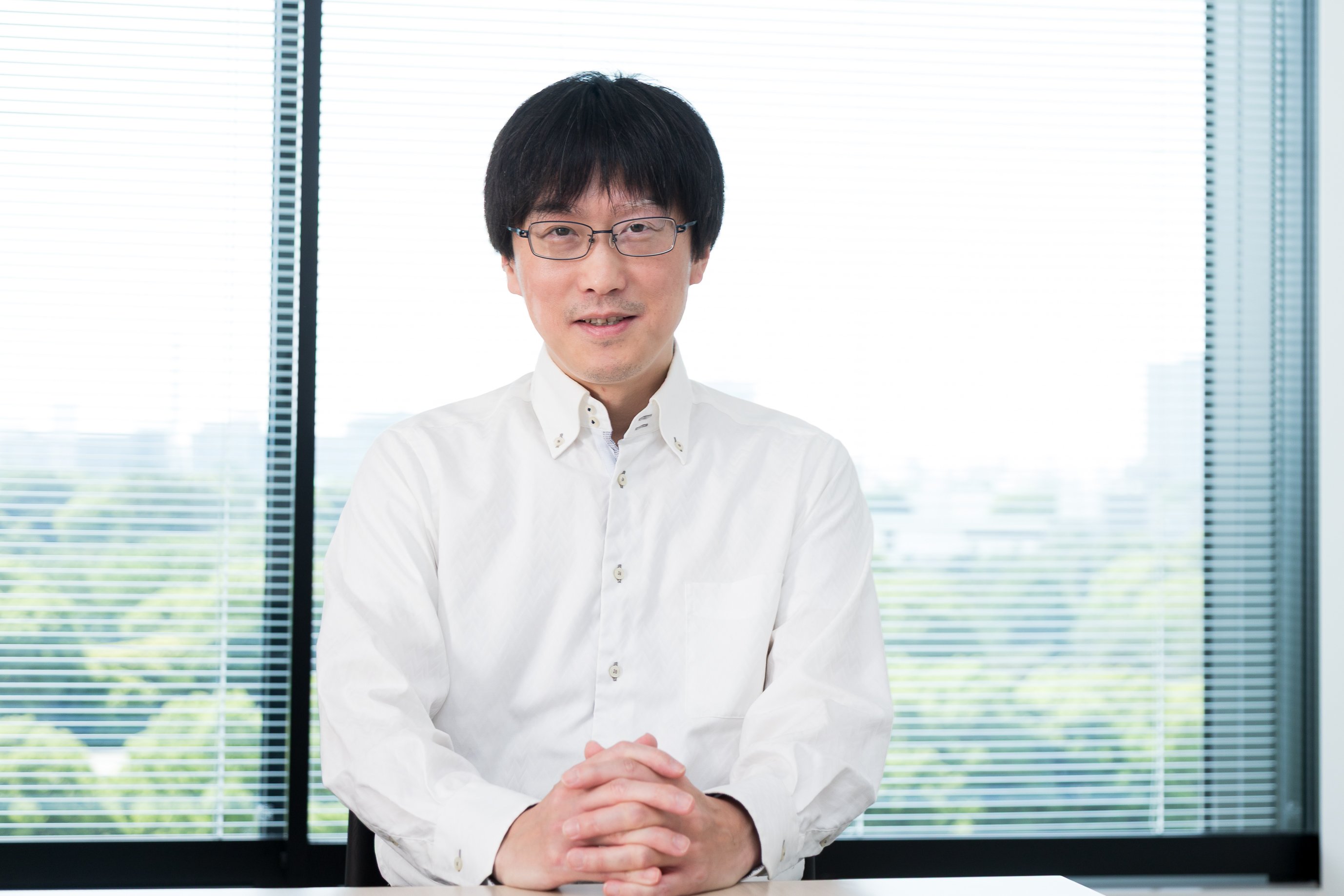

Japan, UiPath
Get articles from automation experts in your inbox
SubscribeGet articles from automation experts in your inbox
Sign up today and we'll email you the newest articles every week.
Thank you for subscribing!
Thank you for subscribing! Each week, we'll send the best automation blog posts straight to your inbox.