UiPath Blog
AI時代に改めて考えるBPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)
Share at:
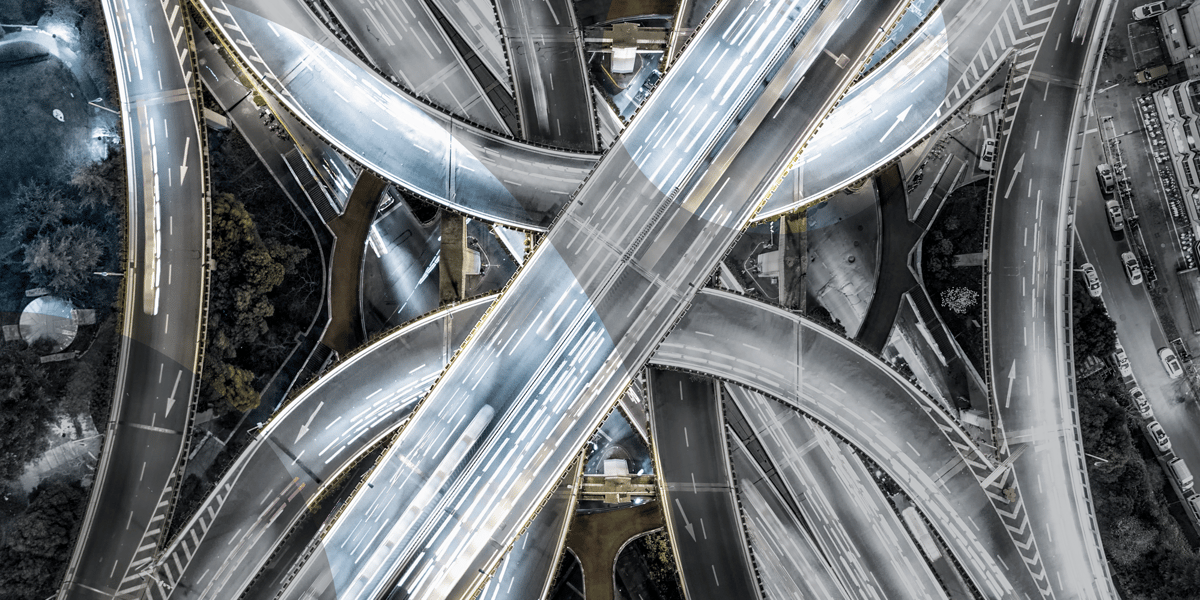
乱立するAIから『業務の設計図』を取り戻そう!
はいどーも、こんにちは!Agentic Automationセントラル・チームです! 今日は『AI時代に改めて考えるBPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)』というタイトルで、、BPMの話をします!
BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)とは?
ビジネスプロセス管理(BPM)は、ビジネスを運営する上で関係するすべてのプロセスを継続的かつ反復的に改善するための一連の技術です
OMG(Object Management Group)のブローシャによると、上記のような定義がされています。ちょっと抽象的なところもあるので、もう少し具体的に言うと
業務フローを描いて(自由に描くのではなく、ちゃんと様式に則る)
業務フローに沿って業務を処理して
かかった時間などを分析して継続的に改善する
といった一連の仕組み・取り組みを指しています。
これだけを見ると良いことしかないような気がしますが、実際には日本ではあまり流行りませんでした。どれだけ流行らなかったのか?なぜ流行らなかったのか?ちょっと考察してみましょう。
日本ではイマイチ流行らなかったBPM
市場規模のデータは調査会社によって計測方法が違ったり、そもそもの数字が公開されていなかったりするので、正直、調査が難しかったりするのですが、たとえばITRの2011年のプレスリリースを見てみると、BPM/BAMソフトウェア(BAMというのはBusiness Activity Monitoringの略で、先ほどの3つ目のステップ(かかった時間などを分析して継続的に改善する』を支えるITシステムの機能です)市場の規模は61億円、前年比17.9%増です。市場規模は正直、かなり小さいですが、成長率は悪くない印象です。
ところが、これが2014年のプレスリリースとなると『2014年度は1.7%増とほぼ横ばい、市場は停滞気味に』になります。3年で完全に失速してる、、2019年になるとRPA/OCRの付属品のような扱いになり、その後は数字もわからずじまい。日本では2010年代の序盤こそ良かったものの、あまり爆発的な成長はしていない印象です。
では海外(欧米)ではどうなのか。海外のBPMソフトウェア市場の状況を知ることは容易ではありませんが、たとえばCamundaというソフトウェアの成功には目を見張るものがあります。同社は2008年に創業し、2021年には$21.3M(約31億円)の売上(ARR)がありましたが、2024年には$100M(約147億円)に到達したと発表しています。この大きな成功は間違いなくCamundaの優位性によるものだと思いますが、市場がほとんど成長していない状況で、このようなことを達成することは困難です。海外のBPMソフトウェア市場自体は、日本とは異なり、かなりの成長をしていると予想できます。
なぜ日本でBPMは流行らなかったのか?
『日本は特殊な国』とよく言われますが、なぜこのようにBPMの導入に違いが出るのでしょうか?ネット上には様々な意見があるようです。
仮説1:そもそも欧米は規制対応(SOX、GDPRなど)がBPM導入を後押ししている。日本にも規制(JSOXなど)はあるが、罰則が弱くBPM導入の動機になりにくい
仮説2:欧米には業務とITの両方を使いこなす人材の割合が日本よりも多く、BPM導入を進めやすい(つまりこれはリテラシーの問題)
仮説3:そもそも日本では標準的な業務プロセスなど存在しない。業務プロセスに人が従うのではなく、個人に業務が従属している
どれもありそうな話です。ここに加えて、私の個人的な体験も少し共有させてください。私は以前、製造業のお客様の仕事をさせていただいたことがありました。そのお客様はいわゆる伝統的な日本の大企業でしたが、経営統合があり、欧州に本社が置かれることになりました。そうなると日本と欧州で様々なコミュニケーションが発生しますが、盛んにそこで言われていたのは『標準的なフレームワークに基づいて…』という話でした。欧米は多様な背景・文化を持つ人・組織と仕事をするので、なんらかの共通的な物差しが必要なんだと思います。
しかし一方で、そこで思ったのは『日本の組織・文化においては標準的なフレームワークという存在は、まだるっこしい手順で、やりたくないし、慣れてないことなんじゃないか?』という仮説です。わざわざ標準的なお作法を勉強して、それに則って何かを定義して、立派な文書をみんなで読み込んで、それをベースに議論しなくても、たばこ部屋に行ってお互いの事情に忖度し、『オレんとこも辛いが、君んとこも大変なんだな。よし、じゃあ今回はここで手を打とうじゃないか』と話せば5分10分で決着できるだろう、と。確かにそういう状況だったら、かえってBPMをやるほうが面倒だし、誰も使わなくなっちゃいますよね。
これからの日本:BPMの再評価が必要だ
ただ、そういったやり方は、皆様もご承知の通り、だんだん難しくなってきています。理由はいくつかありますが、何よりもまず、昨今の少子高齢化・人手不足を考えると、阿吽の呼吸で仕事ができる同質な人材で構成された職場を維持していくのは困難でしょう。異なる背景・文化の人たちと、標準的なフレームワーク(共通的な物差し)でコミュニケーションをし、合意形成をしていく必要があります。
そして、この多様になっていく職場に、AIが加わってきます。日本でのAI活用はまだまだで、欧米よりも遅れていると報道されていますが、今後、AIの普及の流れは止まらないと思います。そうなったときに、人の業務、あるいは業務プロセスの一部がAIによって代替されていくわけですが、AIの導入の統制を取ることはかなり難しく、実際は様々な見えたり・見えなかったりするAIがバラバラと業務に導入されていくでしょう。あまり良い言葉ではありませんが『Shadow AI』という言葉も一部では唱えられています。AIのセキュリティ、AIがアクセスするデータやシステムの適切な権限管理、AIの結果に対する責任の所在など、業務上のリスク管理が必要です。
業務プロセスという『業務の設計図』がしっかりと定義され、実行結果をモニタリングできる仕組みは、人口減少とAI活用が進むこれからの日本において必須であり、かつて日本では流行らなかったBPMによって実現できるのではないでしょうか。
まとめ
BPMとは業務プロセスの可視化と実行の分析を通して、業務の継続的な改善を行う仕組み
日本ではBPMは2010年代に少し注目されたが、その後、伸び悩んでしまったように見える。一方で欧米では成長し続け、爆発的に成長するBPMソフトウェアも登場した
日本でBPMが流行らなかった理由は様々に予想できるが、それは日本企業の組織や文化に紐づいているだろう
日本を取り巻く現状は変わってきており、特に少子高齢化・人手不足とAI導入の広がりはBPMが日本で再評価されるきっかけになる

Japan, UiPath
Get articles from automation experts in your inbox
SubscribeGet articles from automation experts in your inbox
Sign up today and we'll email you the newest articles every week.
Thank you for subscribing!
Thank you for subscribing! Each week, we'll send the best automation blog posts straight to your inbox.

